2
俺はアパートに帰る前に、サブを連れてコールマン博士の研究所に向かった。
俺は新海涼。警視庁特別捜査課勤務、27歳独身、中肉中背で、人に言わせると善相というやつなんだそうだ。たいしていい顔とはいえんが、自分ではなかなかシブくまとまっていると思っている。
特捜課、通称テクノポリス、は、設置されてまだ2年ちょっとの、新しい課である。
ここが他の課と違うところは、5年ほど前から試験的に導入されていた、アシスタントアンドロイド(A・A)を本格採用している点にある。
A・Aは、標準型で重量約200㎏、身長2m強、動力は原子力電池。耐エネルギー線装甲出、通常の弾丸くらいでは簡単に破壊されないボディを持っている。
ただ、現在の電子工学をもってしても、高度な判断力を持つ電子頭脳を、アンドロイドに搭載可能なほど小型化することはできず、メインブレーンが警視庁に置いてあって、それと常時マイクロ波で接続されている。
警視庁のデータバンクと直結されているため、犯罪捜査においては、すばらしい機能を発揮する。
俺のパートナー、サブはA・AではなくA・R(アシスタント・ロボット)である。
A・RはA・Aの初期型で、機能的にはA・Aとなんら変わりはないのだが、外観がロボットそのものなのだ。サブはARー003、現在、警視庁で使用されているA・Rの中で一番古い。
こいつを製作したのが、テクノポリスの技術顧問として、5年前、日本に招かれたニール・コールマン博士なのだ。
天才的な原子工学者であり、技術者であるコールマン博士が全力をあげて製作したプロトタイプだけあって、サブの機能は最近のA・Aと比べても、まったく見劣りしない。かえってサブの方が、優秀な部分も多い。
問題はサブの外観と個性だ。
コールマン博士は、かなりの変わり者で、「ロボットはあくまでロボットなのだから、人間に似せる必要など無い。アンドロイドなんぞ、もってのほかだ」と力説する人物である。そのおかげでサブは、昔考えられたロボットのパロディのような外観になってしまった。
声も同様、どこか間の抜けたような声、しかも、妙に人の揚げ足を取るいう、やっかいな癖まで持っている。
最新型のA・Aの味もそっけないセッティングよりはましだが、少々行き過ぎの感がある。チンドン屋みたいに色とりどりのブリキカンのお化けを連れて歩く、こっちの身にもなってほしい。
そこら辺をどうにかしてもらおうと思って、たびたび博士の研究所を訪ねてはいるのだが、今のところ、博士は全く取り合ってくれない。
まあ、この博士のところに通うのは、もう一つ、別な理由があるのだが・・・。
「今日ハ、何ノタメニ、博士ノトコロヘ、イラッシャルノデスカ」
サブが、相変わらず間の抜けた声で言い出した。
「決まっているだろ。お前のそのしゃべり方、もう少し、ましにしてくれって頼みに行くんだよ」
「私ハ、無駄ナコトダト思イマスガ」
「わからんだろうが、もしかしたら、急に博士の気が変わるかもしれん」
「ソレヨリモ別ナ理由ガアルノデハアリマセンカ? タトエバ、パメラ・コールマンニ会イタイトカ」
サブは人間くさい、冷やかすような口調で言った。こういう時、表情などあるはずのないサブの顔までが、妙に人間くさく見えてくるから不思議だ。まるで、うすら笑いを浮かべているような・・・。
図星をさされた俺は、あわてて何が言い返そうとしたが、やっぱりやめた。
口げんかでサブにかなうはずがない。なによりも、刑事がエアカーの中でロボットと口げんかしているなんて、考えただけでもみじめだ。
俺は黙り込んでエアカーを操った。
コールマン電子工学研究所の駐車場にエアカーをすべり込ませ、軽い足取りで玄関に向かう。
その俺の様子をじっと見ていたサブは、再び、ひやかすような口調で言った。
「リョウ、ネクタイガマガッテイルヨウデスガ」
俺は反射的にネクタイに手を伸ばした。
ネクタイは曲がっていなかった。
睨み付ける俺を無視して、サブはさっさと玄関に行きブザーを押した。
ところが、なかなかドアが開かない。いつもなら、1分もしないうちにサーバントロイド(召使いアンドロイド)がでてくるはずなのだが・・・。
もう一度、ブザーを押そうとして、ドアに近づいたとき、突然勢いよく、ドアが開いた。
当然、ドアは俺の額にモロにぶち当たる。
「あら新海さん、いらっしゃい」
流ちょうな日本語と共に、燃えるような赤い髪に、灰色の瞳の娘が顔を出した。
コールマン博士の一人娘、パメラ・コールマン。
「あら、ぶつけちゃったかしら。ごめんなさいね」
俺が額を押さえているのを見て。パムはクスッと笑い、それからあわててあやまった。
「い、いえ。たいしたことないです」
俺は笑みを浮かべようとしたが、顔がゆがんだだけで、おそらく笑いには見えなかっただろう。
「ちょうど良かった。さあ、入って」
俺とサブはいつもの応接間に通された。
そこでは、すでにコールマン博士が、アメリカ人にしては小柄な、引き締まったその身体をどっかとソファに沈めて、コーヒーを飲んでいた。一休みしてしたところだったらしい。
「やあ、新海君、サブの改良の件なら、お断りするよ。私は、今のままのこいつが一番気に入っているんでね」
のっけから、こう言われたんでは、話にならない。
サブの方をチラッとみると、黙って胸のランプ群を明滅させているだけだ。ざまあ見ろと行っているように見えるのは、俺のひがみか?
「それよりも、ちょうど良かったよ。今、サブに連絡して君に来てもらおうと思っていたんだ」
「何かあったんですか」
俺が尋ねたとき、俺の分のコーヒーを運んできたパムが答えた。
「いつもなら、キムが玄関に出ていくでしょう。変だと思わなかった?」
「キムがどうかしたんですか」
キムとはコールマン家のサーバントロイドである。
「壊されちゃったのよ、昨夜」
パムは肩をすくめて言った。
「壊された?」
「ええ、昨夜ちょっとお使いに出したら、帰ってこないのよ。パパと捜しに言ってみたら、ここから100mぐらい離れたところで、頭メチャメチャに壊されて、ころがっていたの」
「え、もしかして、それは・・・。」
俺は鞄から、課長に渡された資料を取り出した。
「・・・。たしか、ここ第三分署の管轄でしたよね」
「ああ、一応昨夜のうちに第三分署には届けておいたがね」
「やっぱり・・・」
俺は一通り、資料に目を通してつぶやいた。
「いったい何なの。第三分署の方では、この前の殺人事件で忙しいって、あんまりとりあってもらえなかったんだけど」
パムが、俺の脇に来て、資料をのぞき込む。
「実は、第三分署管轄で、サーバントロイドを壊される事件が六件、立て続けにおきていたんです。それで、テクノポリスの方に出向いて欲しいって要請がありまして、私が行くことになっていたんです。どいうやら七件目が起きたようですね」
「ほう、サーバントロイドが六件、立て続けにねえ。本当にサーバントロイドだけなのかね」
博士が、百円ライターで、缶ピースに火をつけ、身を乗り出してきた。
テクノポリスの技術顧問だけあって、犯罪に対する好奇心は並のものではない。
「うーん、どうやらそのようですね」
俺は資料をめくって、答えた。
「それに、型式も同じですね。全部、マツシタのARA5型か6型のどちらかです。ちなみにこの二つの型は、外観はほとんど同じだそうです」
「ウチのは6型だったわ。いろいろ改造して使ってたけど」
パムまで身を乗り出してきた。
「キムは頭部がメチャクチャになってたけど、ほかのはどうなの?」
「えーと、やっぱり、同じ壊されかたしてる」
「どうやら、同一犯の犯行らしいな」
博士がニヤリとした。
「第三分署では、凶暴な反アンドロイド勢力の仕業だと考えていたらしいんですけど、六件立て続けに起こったもんで、特捜課にまわしたらしいんです。さっき、パムが言ってたけど、例の殺人事件のほうで忙しいそうで」
例の殺人事件とは、この近くのバーのマダムが、ナイフで心臓を一突きされた事件で、三人容疑者がいたものの、みなアリバイがあって、捜査が行き詰まっているらしい。
「同じ型式のサーバントロイドだけ狙うなんて、いったい何が目的なのかしら」
パムは首を傾げた。
「さあ、犯罪には、かならず何か動機があるはずなんだけど」
俺とパムが考え込んでしまったのを見て、博士は両手を大きく広げ、いかにも驚いた、というポーズをした。
「困ったもんだな、お前さん達は、こんな簡単なことも分からんのか?」
そう言うと、博士は大げさにため息をついた。
「テクノポリスがこんなことも分からんようじゃ、犯人になめられるぞ、新海君」
「それじゃ、パパは分かるっていうの?」
パムが憤然とした面もちで言い返した。
「ああ、犯人の名前や人相までは分からんが、少なくとも動機と目的だけは明々白々だね。ちょっと待っていなさい。次に狙われるサーバントロイドのいる家を教えてやるから」
そう言って博士は立ち上がり、部屋を出ていった。
俺とパムは茫然として顔を見合わせた。
10分程で、博士は一枚の紙と地図を片手に現れた。
「さーて、これがこの近くのマツシタARA5型、あるいは6型のサーバントロイドの持ち主のリスト、そしてこれがこの付近の地図だ」
博士がテーブルの上に地図を広げてみせる。
「パム、持ち主の住所を読み上げるから、印を付けていってくれんか」
「そのリスト、いったいどこから持ってきたんです?」
俺はあまりの早さに驚いて尋ねた。
明日、一日かけてそいつを調べる予定だったのだ。
博士は笑って答えた。
「マツシタアンドロイドには知り合いが多くてな。すぐに調べて電送してもらった。じゃ、始めるぞ。まず、新宿A町3-5、亀山直也、同じく26-7-4、鈴木優二、B町15-2、斎藤厚子・・・」
計15個の赤丸が地図の上に記された。
「新海君、壊されたサーバントロイドの持ち主を読み上げてくれ」
俺は第三分署の資料を取り上げ、事件の起こった順に読み上げていった。
「よし、大体のパターンはつかめた」
満足そうな笑みを浮かべ、地図の一点を指さす。
「この地点を起点にして、順々に西の方に向かって壊して言っている。昨夜はウチだった。とすると、次はおそらくこの家だろう」
博士は、この研究所の近くのまだ番号のついていない赤丸を指示した。
「はあ、分かりましたが・・・。動機はいったい何なんです」
「そうよ、勿体ぶらないで教えてくれたっていいじゃない」
「はてはて、頭の働きの悪い連中だな」
博士はソファにふんぞり返って嘆いた。
「ちょっと待ってくれ。名探偵にはタバコがつきものだ」
そう言って博士はタバコに火をつけ、深々と吸い込んだ。
冗談じゃない。名探偵なら、パイプか葉巻が相場だ。缶入りピースに百円ライターで火をつける名探偵がどこにいる?
「さて、犯人の目的だが、これは頭部を破壊しているところから見て、電子頭脳の破壊だろうな。もちろん、動機はこの辺りのサーバントロイド、マツシタARA5型か6型のどれかが持っている、あるデータを消し去るためだ」
「はあ、なるほど・・・。犯人はどのサーバントロイドがそのデータを持っているか分からないから、この辺りのサーバントロイドをすべて壊してしまおうとしている。そういうわけですね」
「そう、その通り」
「ちょっと待ってよ。でも・・・」
黙って聞いていたパムが口をはさんだ。
「でもパパ、あの型のサーバントロイドのデータバンクは、確かスペースの関係でボディのほうに搭載されているはずよ」
「そう、そいつがおもしろいところなのさ」
博士はそう言って、まるでいたずらっ子のように目を輝かせた。
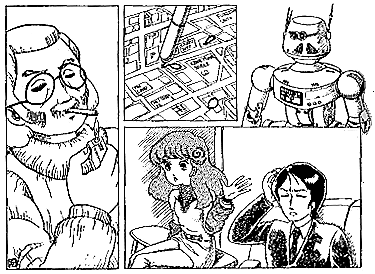
俺とサブはその夜、博士に教えられたB町15-2のある女流作家の家に張り込んだ。
事情を話すと、彼女は喜んで協力してくれた。ネタにするつもりなのか、根ほり葉ほり聞いてメモをとっている。さすが作家は違うものだ。
門の植え込みの影に、サブとしゃがんで隠れた。
夜の張り込みでタバコを吸うわけにもいかない。俺は暇を持て余して、サブに小声で話しかけた。
「おい、サブ。お前は今度の事件どう思う」
サブはしばらく黙り込んでいたが、考えがまとまったらしく、
「ワタシハ・・・」
と話し始めた。一緒に胸のランプを明滅させ始めたので、俺はあわてて、
「こら、ランプつけるのはやめろ!」
としかりつけた。
「ワタシニハ、犯人ヲ掴マエルコトガ、ダイイチデス。別ニ、ドウ思ウカト言ワレマシテモ、答エヨウガアリマセン」
「壊されたのはお前の仲間のアンドロイドだぞ。俺が殺人犯を憎むような気持ちは起きんのか?」
サブは何か言いかけたが、また黙り込んでしまった。
のってこないのではしょうがない。二人とも黙ったまま、じっと時がくるのを待っていた。
PM10:00、玄関が開いて、女流SF作家が使っているマツシタARA5型が姿を現した。近くに買い物に行かせるよう、頼んでおいたのだ。
170㎝ほどのプラスティック製のボディを持ったサーバントロイドが軽い足音をたてて、夜道を歩いていく。
家の角のところから、一人の男がサーバントロイドの後をつけ始めた。
俺とサブは顔を見合わせ、うなづいた。
俺とサブは30mほど離れて尾行していった。
俺もサブも、ほとんど足音はたてない。
しばらく歩くと、サーバントロイドは人通りの少ない倉庫街にさしかかった。
男が動いた。
棒状のものを振りかざし、サーバントロイドに後から飛びかかっていく。
俺は間髪を入れず、手に持っていた衝撃銃を撃った。
男は青白い光をあびて、うつ伏せにバッタリと倒れた。
「ご苦労さん、もう家に帰っていいよ」
俺は男が倒れたところに急いで駆け寄り、そこに立っていたサーバントロイドに言った。
「ハイ、ホカニ御用ハ?」
「ない。ご主人に無事逮捕できたって伝えてくれ」
「ワカリマシタ」
サーバントロイドは、何事もなかったように夜道を家に戻っていった。
俺が倒れている男に近寄ったとき、男をあおむけにして顔を確認していたサブが、胸のランプを激しく明滅されながら話し始めた。サブが興奮(と言っていいかどうか分からんが)している証拠だ。
「オモシロイコトガ、ワカリマシタ。コノ男ハ、今野誠一トイッテ、一ヶ月前ニコノ近クデオキタ殺人事件ノ容疑者ノウチノ一人デス」
「なんだって!」
俺は驚いて、サブのハンドライトに照らされた男を見つめた。